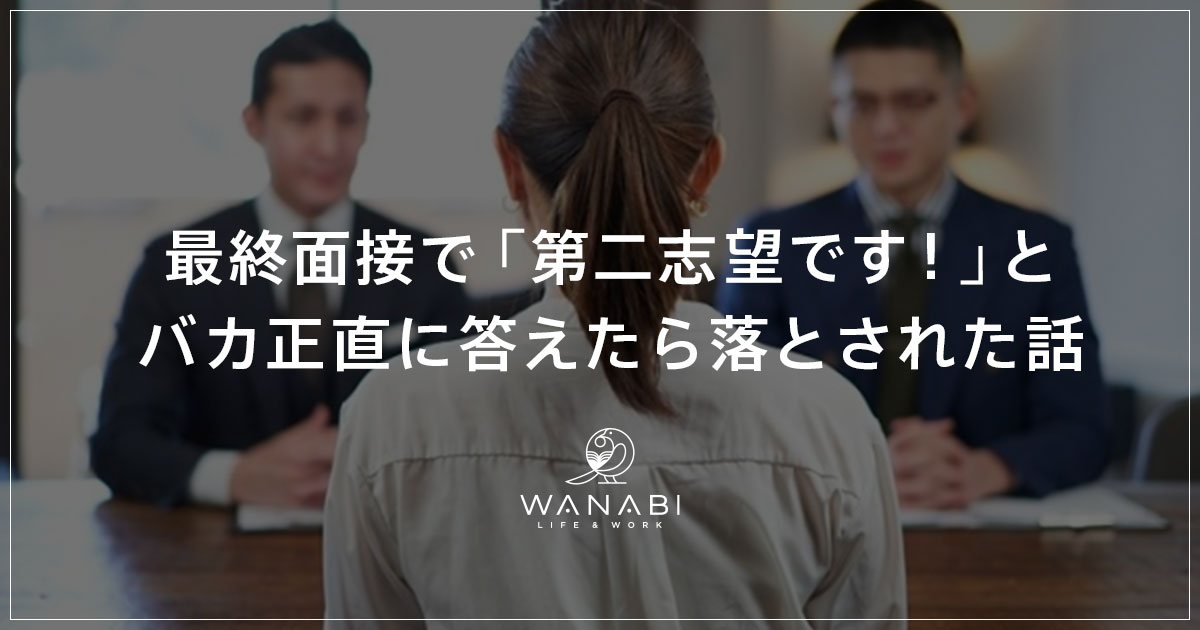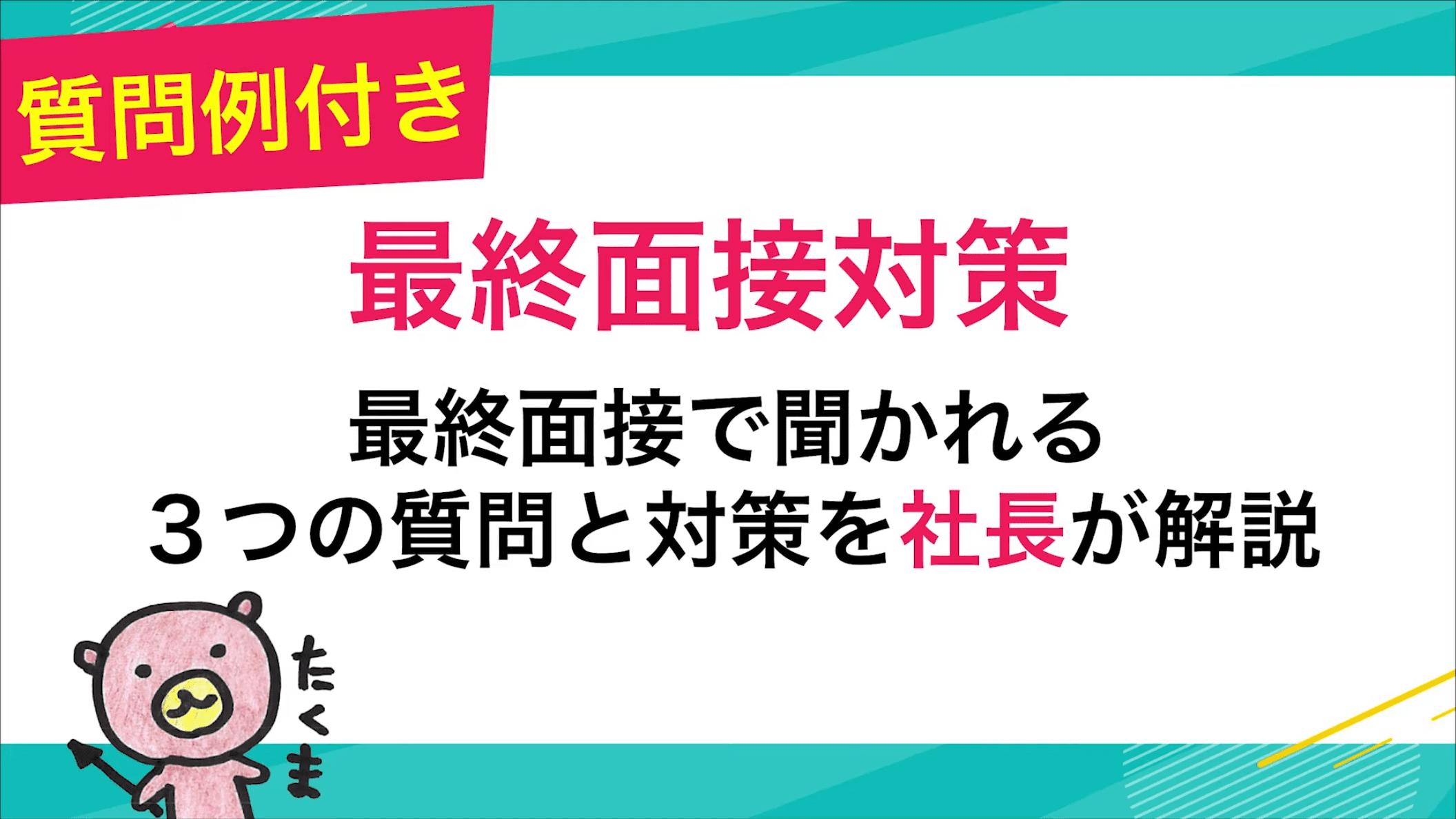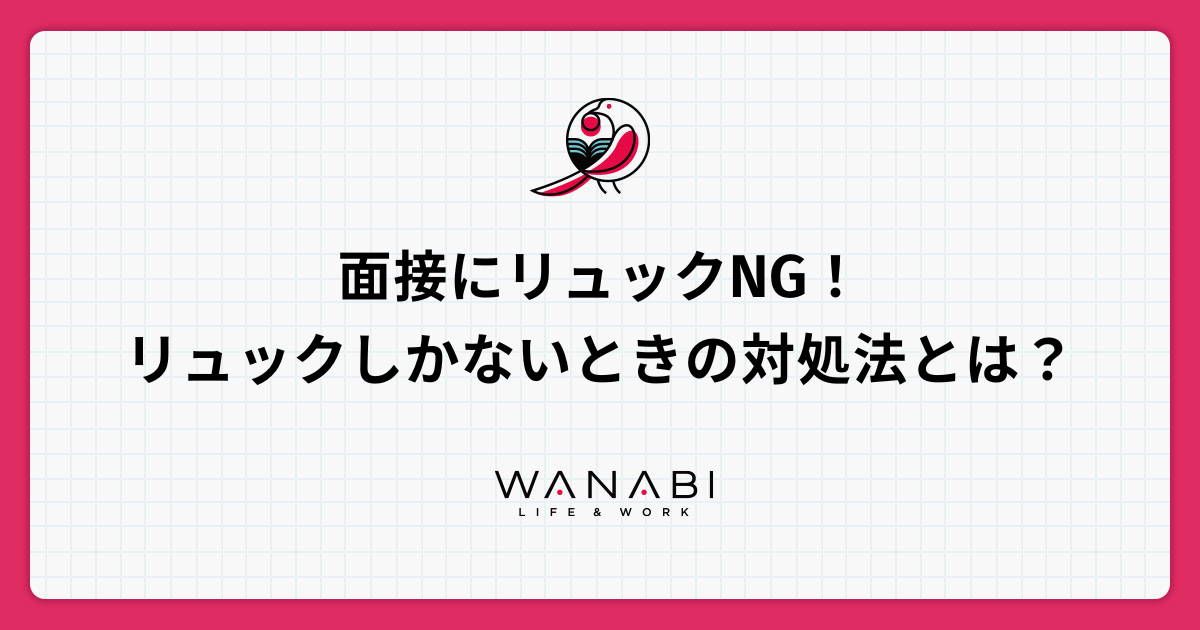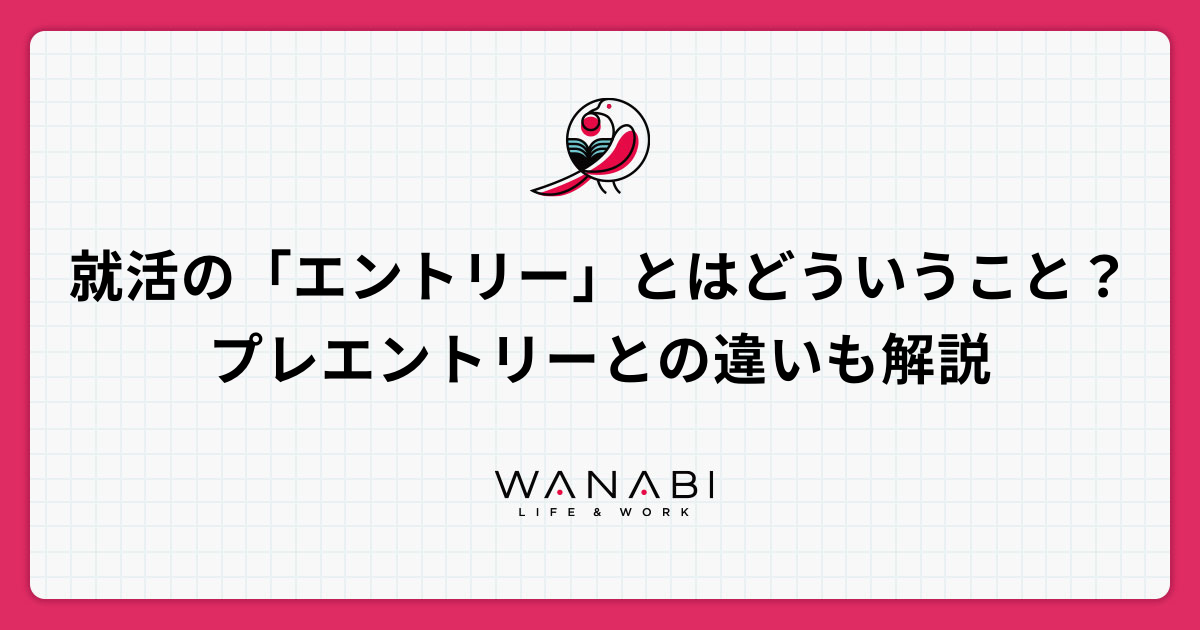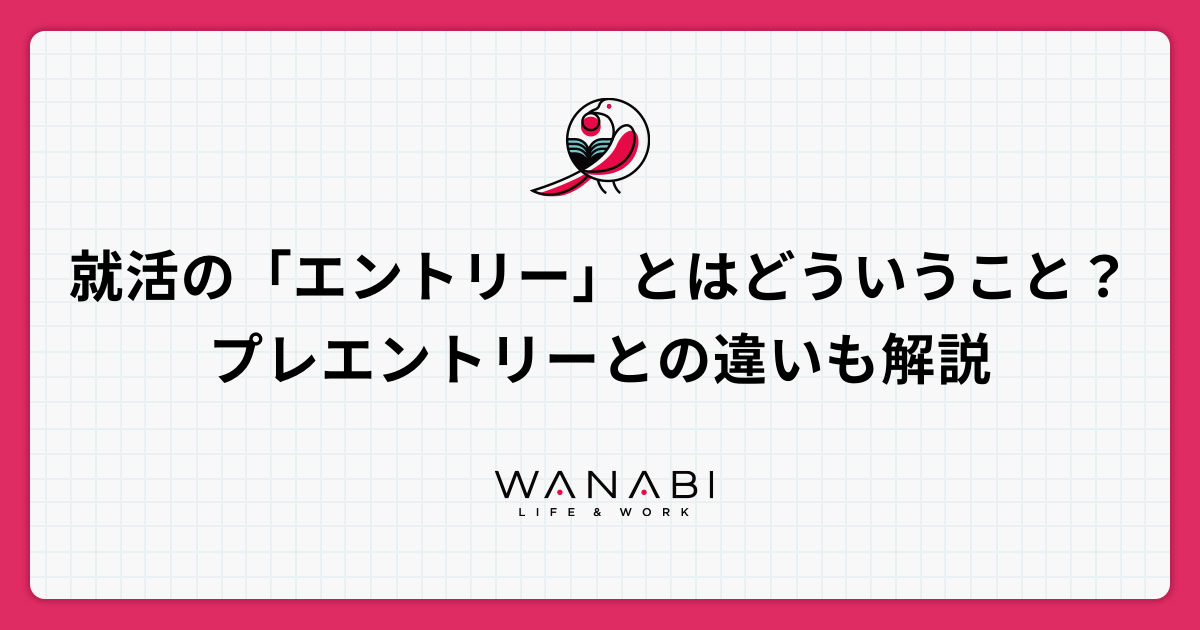
就活をはじめると、耳にすることが急に増える「エントリー」という言葉。
就活ナビサイトには「まずは企業にエントリーしましょう!」と書いてあったり、友人から「何社エントリーした?」と聞かれたりすることがあると思います。
しかし、一概に「エントリー」と言っても、「プレエントリー」「本エントリー」「インターンシップエントリー」などとさまざまな表現があって、困惑する方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな就活における「エントリー」という言葉の意味や方法、効率的に就活するためのコツをご紹介していきます。
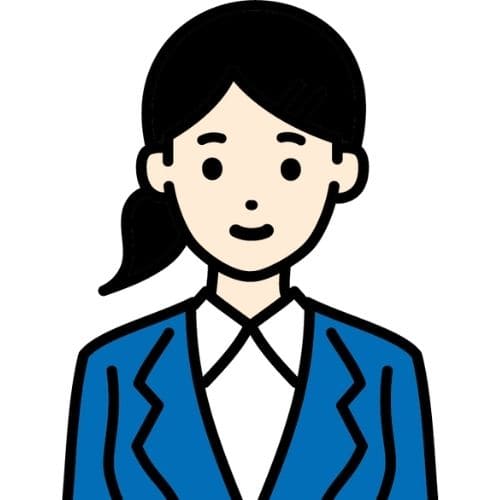
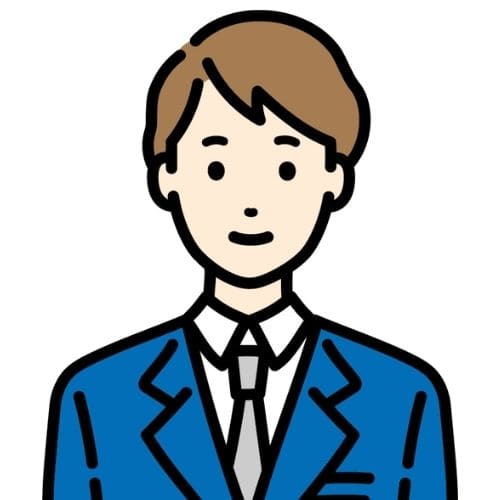
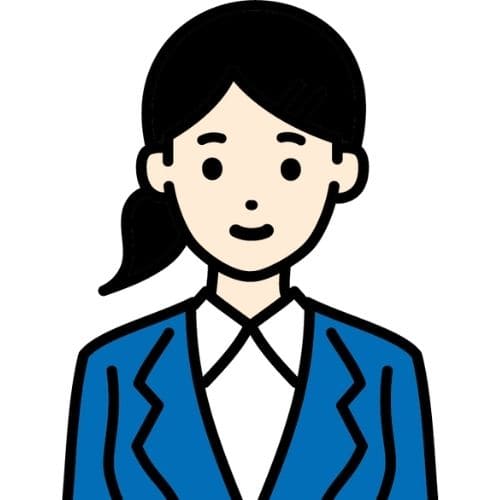
などの悩みを持っている方に、ぜひ読んでほしいです。
「エントリー」ってどういう意味?
はじめに、わかっているようできちんと理解している人が少ない「エントリー」の意味について説明していきます。
エントリーといっても、いろんな表現があったり、ナビサイトによって意味が違ったりします。
エントリーを効率的におこなうためにも、まず、エントリーという言葉の意味を正しく理解していきましょう。
エントリーとは、企業に興味があると意思表示すること
エントリーとは、学生が企業に対して興味があると意思表示をすることです。
エントリーすることによって、
- 名前
- 大学・学部
- 住所
- 電話番号
といった個人情報が企業側に公開されます。
また、学生はインターンシップや選考開始に関する具体的な情報を得られます。
ここで勘違いされやすいのが、エントリーと応募の違いです。
エントリーは選考参加の意思表示にすぎず、正式な応募ではありません。
したがって、エントリーしたからといって、その企業に必ずエントリーシートを提出したり、説明会に参加したりする必要があるわけではないので、安心してください。
反対に、エントリーしたからといって安心しきってしまい、エントリーシートの提出期限を過ぎてしまったり、説明会に応募し忘れたりしないように気をつけてくださいね。
※エントリーと同時にエントリーシートの記入が必須である場合もあります。企業によって違うため、その都度確認するようにしましょう。
本エントリーとプレエントリーの違い
エントリーの意味について、理解できましたか?
エントリーと言っても、いろいろな種類があります。
次に、本エントリーやプレエントリーなどの細かい違いについて説明していきます。
エントリー
エントリーは、先ほど説明したように企業に興味があると意思表示することです。
本選考におけるエントリーの受付開始時期は、就活解禁の3年の3月で、インターンシップのエントリーは、3年の6月からです。
※外資系やベンチャー企業の場合は、本選考解禁が早いため、3年の夏ごろにエントリーできることも多いです。
エントリーをしたら、以下のことが可能になります。
- 最新の選考情報が届く
- 説明会の予約が可能になる
- 企業情報が載った資料がもらえる
- ESの提出や、筆記試験の受験が可能になる
企業の情報を得るためにも、興味がある企業にはまずエントリーすることから始めましょう!
本エントリー
本エントリーとは、企業の選考に正式に応募することです。
実際にエントリーシートや履歴書を出したり、面接を受けたりできます。
- エントリー=企業に興味があると意思表示すること
- 本エントリー=エントリーシートを提出するなどして企業に正式に応募すること
という風に、意味が違うので気をつけてくださいね。
エントリーと大きく違う点は、すでに選考フローに乗っているため、辞退の連絡が必要という点です。

プレエントリー
プレエントリーは、就活解禁前(あるいはインターンシップ解禁前)に、前もってエントリーを予約しておくことをいいます。
プレエントリーした時点では、企業側に学生の情報は伝わりません。
就活解禁(3月1日)、またはインターンシップ解禁(6月1日)を迎えたときに、企業に情報が送信されます。
※基本的に、プレエントリー=エントリーの予約と考えるとよいですが、プレエントリーとエントリーを同じ意味で使うことも。ナビサイトによって厳密な意味は違うため、使っているナビサイトの定義を確認しておいてもよいですね。
インターンシップエントリー
インターンシップエントリーは、文字通りインターンシップにエントリーすることです。
インターンシップのエントリーのなかに、プレエントリーとエントリー、本エントリーの3つにわけられます。
インターンシップ解禁前の3年の5月31日までにできるのが、「インターンシップのプレエントリー」、6月以降には「インターンシップのエントリー」をするといった形になります。
その後ESを提出したり面接を受けたりすることが「インターンシップの本エントリー」に当たります。
こちらも先程お伝えしたように、プレエントリーやエントリーをしたからといって、必ずしもエントリーシートを提出したり、インターンシップに参加したりしなくても問題ありません。
※企業によっては、エントリーと同時にインターンシップの志望動機を記入しなければならないところもあるので、注意してください。
あらかじめエントリーしておかないと、インターンの選考情報が届かないこともあります。
気になる企業のインターンシップの参加チャンスを逃さないためにも、興味がある企業には気軽にエントリーしておくのがおすすめです。
エントリー方法は企業や媒体によって違う
エントリーの方法には、大きく5種類あります。
- ナビサイトを使う
- 企業の採用ページで直接情報を記入する
- スカウトアプリを使う
- 合同説明会に参加する
- 人材紹介エージェントを使う
それぞれエントリーの方法が違うため、1つずつ説明していきます。
ナビサイトを使ってエントリー
ナビサイトは、リクナビ、マイナビが有名です。ワンキャリアやあさがくナビ、キャリタスを使う学生も多いですね。
ナビサイト上で気になる企業を見つけたら、エントリーボタンを押すだけで簡単にエントリーできるものが多いです。
ナビサイトの登録時に記入した情報が、エントリー企業にも送信されます。
企業にエントリーするたびに、毎回情報を入力する必要がないので、手間が少なくエントリーできるところがポイント。
採用サイトで直接エントリー
企業のHPや採用ページで直接エントリーする方法もあります。
ナビサイトには載っていない企業にエントリーする際は、このやり方をするとよいでしょう。
まれに、ナビサイト上では募集が締め切っていてエントリーできない場合でも、採用サイトではまだ間に合うことがあります。
企業ごとに情報を記入しなければいけない手間があるので、多くの企業に直接エントリーするのは大変な作業になります。
そのため、ナビサイトと併用して使い分けるのがおすすめです。
エントリー後、情報が来るのが遅い場合もある

スカウトアプリを使う
ナビサイトとはまた別の、スカウトアプリを使ってエントリーするという方法もあります。
オファーボックスやキミスカ、inteeなどが有名です。
こちらは企業が学生に対してスカウト(オファー)をくれるものです。数多くの企業のなかから、学生側がエントリーする企業を選ぶナビサイトとは異なります。
学生は、企業からスカウトをもらったあと、エントリーするかどうかを自分で決められます。
エントリーをすると、企業の採用担当者と直接メッセージのやり取りができるようになります。そのやり取りを通して、説明会の予約や面談の日程調整をしていきます。
こちらもナビサイト同様、スカウトアプリを登録した際に記入した基本情報が、エントリー先の企業に送られるシステムになっているため、効率的にエントリーすることができます。
ただ、理想の企業にスカウトをもらえるとは限らないため、気になる企業にはナビサイトなどで自分からエントリーしましょう。
サイトに登録するだけでスカウトがもらえる
合同説明会・イベントに参加する
合同説明会やイベントに参加することで、企業にエントリーするやり方もあります。
合同説明会や就活イベントに参加すると、複数の企業の話を聞く機会があります。そこで興味を持った企業には、エントリーの意思表明ができます。
イベント中の学生の行動や態度を見て、スカウトをもらえるイベントなどもあります。ジョブトラといわれる「ジョブトライアウト」などのイベントが有名です。
一日で6社など、複数の企業に効率的に出会えるチャンスになるのが、合同説明会やイベントの魅力。
対面だけでなく、オンライン開催のものもあるので、気軽に参加してみてはいかがでしょうか。

人材紹介エージェントを使う
人材紹介エージェントを使って、企業にエントリーするという方法もあります。
人材紹介エージェントとは、面談などで学生の趣向や性格を見たうえで、その学生に合った企業を紹介してくれるサービスです。
こちらもナビサイトなどのように、サービス登録の際に記入した情報がそのまま紹介先の企業に送られるため、エントリーの手間が省けます。
面談担当のスタッフに、就活相談にのってもらえることも多いため、誰かに相談しながら就活を進めたい方におすすめです。
エントリーに関するよくある疑問
エントリーの意味や種類について、イメージはついてきましたでしょうか。
「エントリーの意味はわかったけど、エントリーするのにまだ抵抗がある…」という方もいるかもしれません。
そんな方のために、ここからはエントリーにまつわるいろいろな疑問にお答えしていきます。
企業に内定をもらうために、エントリーは必ず通らなくてはならない道です。
積極的にエントリーするために、エントリーにまつわる不安を払拭させましょう!
エントリーしたら絶対受けなきゃいけないの?
エントリーをしたからといって、必ずしもその企業にエントリーシートを出したり、面接を受けたりしなければならないわけではありません。
エントリーをした後、その企業の情報を見て自分に合うか考えたうえで、応募するかどうか判断できます。
そのため、基本的にエントリー後、エントリーシートや履歴書を出す前の段階では、辞退の連絡はしなくても問題ありません。
しかし、企業によってはエントリー後、定期的にメッセージや電話で説明会の案内などをしてくれる場合もあります。
「エントリーしたけれど、もう企業を受ける気はない」という場合は、はっきりと「辞退したい」という旨を伝えるようにしましょう。
また、実際に面接に進んだり、インターンシップの参加が決まったりしている場合は、辞退する際に必ず連絡を入れてくださいね。

同じ企業に複数の媒体からエントリーしてもいいの?
さまざまなナビサイトを使っていると、別の媒体から同じ企業を見つけることもあるでしょう。
すでにエントリーしている企業から、スカウトをもらうこともあります。
そんなときに浮かぶのが、「複数のナビサイトから同じ企業にエントリーしたほうがいいのか?」という疑問です。
こちらに関しては、むやみにエントリーしなくてよいが、してしまっても問題はないというのが答えです。
とくに、スカウトアプリにおいては、スカウト限定の特別選考などが用意されていたりします。
それを、「すでに別の媒体でエントリーしてるから、スカウト承認しなくてよいか」とスルーしてしまうのはもったいないです。
しかし、企業側も学生の情報を管理するうえで、同じ人が2重エントリーするのは好ましくありません。
スカウト承認・エントリー後に、「すでに〇〇(サービスの名前)というサイトからエントリーしております。」と一言伝えるとよいでしょう。
それ以外の場合は、基本的に1つの媒体からエントリーできていれば十分なので、必要以上に同じ企業に何度もエントリーしなくても大丈夫です。
エントリーまでにするべきことって?
「エントリーをする前に、何か準備をしなければいけないのでは…」と不安になると、なかなかエントリーする勇気が出ませんよね。
結論として、エントリーに特別な準備は必要ありません。
志望動機などの準備ができていなくても、エントリー後にエントリーシートを提出するまでに準備ができます。
また、エントリーの条件としても、新卒採用においては大学卒業見込み以外の条件は特にありません。
しかし中には、自動車運転免許が必須といった条件や、英語スキルの条件があるので確認しておくとよいです。
看護師や薬剤師、管理栄養士などの専門職は、資格取得が条件なこともあります。企業の選考スケジュールと資格取得日をあらかじめチェックしておき、指定された期日までに資格を取得できるようにしましょう。
何社くらいエントリーしたらいいの?
エントリーする企業数は何社くらいがよいのか迷いますよね。
1人の学生がエントリーする企業数に上限はないため、何社でもエントリーが可能になります。
しかし、上限がないからといってあまりに沢山エントリーしてしまうと、大量のメールやメッセージが届くことになり、選考状況を管理するのが大変になってしまいます。
全国求人情報協会の調査によると、2021年卒の学生で、文系の本エントリー数は14.1社、エントリーも26.7社、理系はエントリー14.7社・本エントリー8.1社だったそうです。
(参考:2021年卒学生の就職活動の実態に関する調査 )
エントリー数のおすすめは30~50社です。多くても100社くらいがよいのではないでしょうか。200社を超えると、情報を管理するのが大変になってしまいます。
適切なエントリー数は人によって違います。
多くの企業を見て自分にあった企業を考えたい人もいれば、じっくりと一社一社吟味したり、選考の準備をしたりしたい人もいるでしょう。
ただ、エントリー数が少なすぎると、あとからエントリーしようと思っても手遅れになるリスクがあります。
まずは、最低でも10社はエントリーしておきたいところです。

エントリーに締め切りはあるのか
エントリーに統一された締切はありません。
企業によって募集締切の時期は違うため、確認しておきましょう。
外資系企業や、ベンチャー企業は採用開始時期が早い分、締切も早いことが多いです。
採用人数が募集人数に達した瞬間に、予定より早くエントリーを締め切ることもあるので、早めにエントリーしておきましょう。
反対に、採用人数を大幅に増やしている成長ベンチャー企業は、4年の夏秋以降にも募集を続けているところもあります。
選考中の企業が0になってしまったり、内定はもらったものの納得するまで他の企業を見たかったりする際には、まだエントリーを受け付けている企業がないか探してみましょう。
- 外資系企業
- 人気の大手企業
- 採用人数が少ないベンチャー企業
- 知名度の低い中小企業
- 事業拡大中のベンチャー企業

エントリー以降のスケジュール
最後に、気になるエントリー後の動きについてです。
本選考エントリー後のよくあるスケジュールは以下の通りです。
↓
説明会参加
↓
書類選考
↓
筆記試験・適性検査
↓
(グループディスカッション)
↓
面接(複数回)
↓
内々定
しかし、これもほんの一例にすぎません。エントリ―後いきなりグループワークの選考があったり、人事との面談があったりと、企業によって採用フローはさまざまです。
エントリー後、説明会を予約する必要があるのか、エントリーシートを提出する必要があるのか、はたまた録画面接を撮影する必要があるのか、次のステップをよく確認して、漏れがないようにしましょう。

効率的な就活をするエントリーのコツ3つ
最後に、効率的にエントリーして就活を進めていくためのポイントを3つお伝えします。
就活中も、時間は有限です。いかに効率的に進められるかが、納得内定獲得のための1つのカギと言えるでしょう。
ただやみくもにエントリーするのではなく、戦略的にエントリーしていきましょう!
アプリを使った一括エントリー
ポイント1つめは、アプリなどの就活サービスを活用した一括エントリーです。
アプリを使うことのメリットは、なにより「基本情報記入の手間が省けること」。
自分の興味のある業界に絞って検索することも可能なので、企業探しからエントリーまでの手間を省き、効率よく就活が進められます。
ナビサイトによって掲載企業も違うため、複数のナビサイトを使い分けるのも賢い使い方だと思います。

エントリー解禁前に目星をつけておく
ポイント2つめは、エントリー解禁前にどこの企業にエントリーするか、目星をつけておくことです。
エントリー解禁日は2種類あります。
- 3年の6月(インターンシップ解禁)
- 3年の3月(就活広報解禁)
「解禁日になってから応募しよう」と思っていると、解禁前のプレエントリーで説明会の参加人数が上限に達して申し込みできなかったなんてことも起こり得ます。
解禁日より前に、自己分析や業界・企業分析をある程度進めておき、気になる企業には早めにエントリーできるようにしましょう。
持ち駒を常に10社くらい持つ
ポイント3つめは、選考中の持ち駒企業を10社くらい持つことです。
就活における持ち駒とは、まだ合否が出ていない志望企業のことをいいます。
就活中に持ち駒が0になってしまうと、また新しく応募し直してエントリーシートを書いたり、企業研究をしなくてはならなかったりと、精神的にも時間的にも余裕を失ってしまいます。
そのため、持ち駒を常に保ち続けること、できれば10社ほどを保つことをおすすめします。
ポイントは、1社落ちてしまったら、1社増やすといったように常に一定数の選考を受け続けることです。
これをやることで、「エントリーしたいけど、どの企業も募集が終わってしまった」「0から企業選びとエントリーシート作成をおこなわなければいけない」といった状況を防ぐことができます。
また、新しい企業にエントリーすることで、今まで知らずにいたけれど自分に合っている企業に出会えるチャンスでもあります。
もちろん、どこか1社に内定をもらえた場合は、無理に持ち駒を増やす必要はありません。
内定をもらう前までは、常に複数の企業の選考を受けることを意識してみてください。

まとめ:興味がある企業にはどんどんエントリーしよう
いろんな表現や種類があってわかりにくい、就活の「エントリー」。
さまざまな方法で、効率的にエントリーできることをおわかりいただけたでしょうか?
今回のポイントをまとめると、
- エントリーとは企業に興味があることの意思表示
- 興味がある企業には早めにエントリーすべき
- エントリーは30~50社、持ち駒は10社がおすすめ
ということをお伝えしました。
エントリーは、就活において避けては通れない道です。
また、自分が将来、晴れて入社する可能性もある企業との、大事な最初の出会いとも言えます。
就活はつらいこと、大変なことも多いかもしれませんが、「企業との新たな出会い=エントリー」を楽しみながら、自分らしい就活を進めていってもらえたら嬉しいです。
みなさんが、自分に合った企業に出会い、納得のいく就活ができることを心より応援しています!